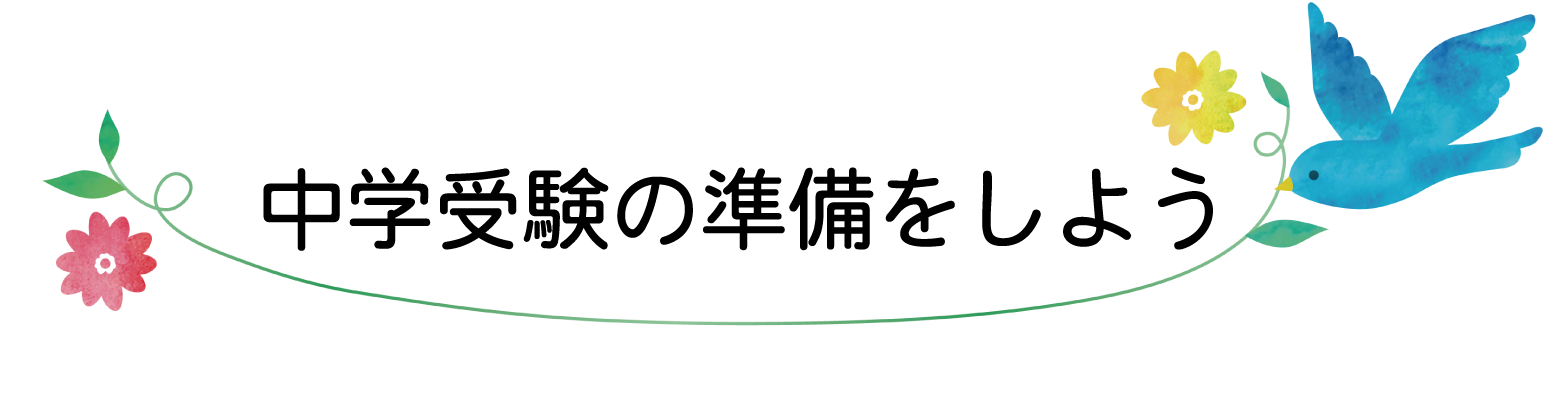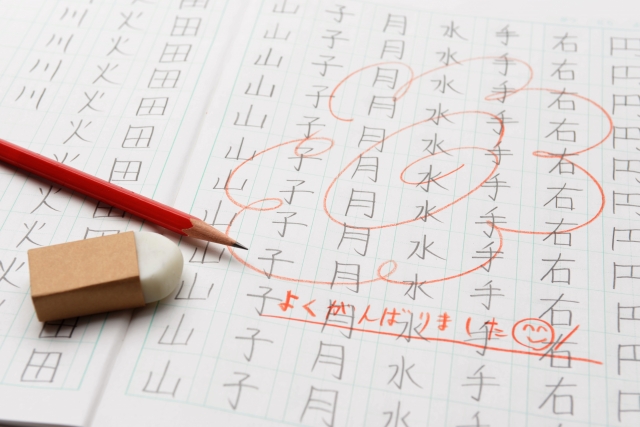余裕がある生活って素敵!
4月に入って、今までのように算数に振り回され、算数に一喜一憂する生活から解放されています。
娘もいつもと違う(算数の勉強時間が少ない)ことに気づいたようです。
春休みに作った貯金があるから、算数の勉強時間が短くてすんでいるんだというと、とても嬉しそうにしていました。
人並みの算数・勉強時間ですんでいる今のうちに、国語を何とかしようと取り組みはじめています。
新しく増やした国語の勉強
今までの国語学習は、予習シリーズの漢字とZ会の中学受験コースだけでした。漢字は朝学習のときに10分くらい、Z会は娘に丸投げ。
漢字はそのままで、Z会は私が隣で張り付いて読み込んでいくスタイルに戻しました。これらにプラスして、今はこの2つのテキストを毎日少しずつやっています。
ふくしま式は1日1ページだけ、花まる学習会の先生テキストのほうは1日に進める量が決められています。2冊やっても15分くらいです。
ふくしま式や出口式もマスターできていないので、花まる学習会の先生のテキストは他と何がちがうか、と言われるとよくわかりません。
それでも娘はとっても楽しそうに解いています。
ドリルは1ページに2問しかないときもあるので、問題集としてのコスパは悪いです。それでもいいと思えるくらい、楽しそうに取り組んでいます。
私も読解の勉強をしながら
私のほうも、大人向けの本を読んで、浅く広い知識を身につけました。
浅く広い知識というのは、国語の読解は奥が深いのでとてもさらっと読んだだけでは使いこなせません。自信はありませんが、4年生レベルならまだ私も解けるので、学びながら我流で教えています。
娘に教えつつ、この2冊を何度も読み返して少しずつ私自身もレベルアップしていきたいです。
私が娘の一番の課題として考えていることは、「意味がわからない言葉が多い説明文のときに、ただ文字を追うだけになってしまうこと」です。
- むずかしそうな文章は、筆者が自分の意見を主張するために書いていること。
- 筆者は自分の意見に説得力をもたせるために、具体例をいっぱい出すこと。
まずはこの2つを徹底的に教え込んでいます。文章中に具体例がはじまったら、「具体例がはじまったね」とイチイチ言っていく感じです。
もちろん接続詞や指示語も、娘が読み飛ばしたらイチイチ横でつっこんで、メモを入れながら読んでいます。
Z会がわが家にはあっている
4月からZ会の4年生 中学受験コースの国語が説明文に入りました。
予習シリーズのほうは物語文なので、今月末の組み分けテストを考えると物語文も気になります。
でも、国語は成績を上がるのに時間がかかると知ったので、説明文を優先させることにしました。
わが家にはZ会のボリュームがちょうどいいです。予習シリーズのほうは文章が長くて、娘の集中力がもちません。
内容も娘にはちょうどいい難易度です。
一人ではスラスラ解けないけれど、私と一緒に丁寧に読んでから解けば、ほぼ全問正解という感じのレベルです。
今は説明文に対して自信をなくしているので、成功体験を詰ませることを第一に考えて進めています。
文章を分解して読むこと
娘が「何をいっているかわからない」となってしまうのは、たいてい具体例をあげている文章です。
知らないカタカナ、読めない漢字、むずかしい言葉などが次々とでてくると、その時点でギブアップしたいですという顔になります。
どうにも無理そうなときは、ここは具体例だということを気づかせた上で、段落の上に『ぐ』と書きこんで、意味がわからなくても気にしないことにしました。
具体例の前後には筆者が言いたいことが書いてあるはず。そこだけはちゃんと狙いをつけてから、具体例の文章は飛ばしてよしとしています。
とりあえず、頭の中がぐちゃぐちゃにならないように、文章全体をつかむ練習をしています。
大事な文章を読み飛ばしたりしないよう、あれこれ私がとなりで言いながらじっくりと読みこめば、あとは早いものです。

自分で論説文もどきを書きはじめた
説明文や論説文、大人が書く文章は、こういう風に書かれていると構造を説明しました。
主張に説得力をもたせるために、あらゆる角度から話をするんだと言うことを伝えると、ちょっと楽しくなってきたようです。
『私とドッチボール』
というテーマで、娘なりに自分の意見を書き始めました。
あちこち話は飛んでいますが、必死で普段は一切使わないであろう『一方で』やら『このように』などを駆使して、ドッチボールが嫌いな理由を具体例をあげながら述べています。
4年生女子なりの主張を読んで、ニヤニヤしてしまいました。
半年後に国語の成績がアップすることを夢みて、国語の勉強をサボさずにつづけてみます。